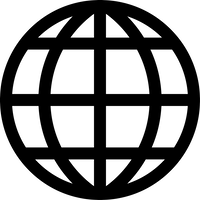2025年7月13日・14日 開催|瀬戸内リトリート青凪「DISCOVER EHIME 2025」宿泊型体験プラン@愛媛 松山市
更新日:2025 - 08 - 22
2025年7月13日(日)・14日(月)、「瀬戸内リトリート青凪」(愛媛県松山市)にて、宿泊型特別体験プラン「DISCOVER EHIME 2025『ここにしかない景色と、ここにしかない手しごと』」を開催いたしました。
本イベントでは、参加者の皆さまが愛媛に根付く伝統の酒造・和菓子・焼き物文化に触れ、その背景にある“人”の想いや物語をじっくりと感じ取ることができるプログラムをご用意しました。
道後で唯一の酒蔵「水口酒造」や、150年以上続く老舗「山田屋まんじゅう」、砥部焼の新風を生む「ヨシュア工房」の職人たちが、それぞれの哲学と技を語り合う特別プログラムが展開されました。(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000129.000118716.html)

■地域文化を『宿』から物語る、新たな挑戦
温故知新はこれまで、ホテルや旅館を単なる滞在場所ではなく「地域のショーケース」と位置づけ、全国各地で旅の目的地となる宿の運営・プロデュースをしてまいりました。
今回のイベントでは、商品や施設のプロモーションにとどまらず、地域で脈々と受け継がれてきた職人の技や想いを、“人”を軸に伝えることを重視。特に今回は、東京など都市圏から地元にUターンし、家業を継いだ若き経営者たちに焦点を当てています。
たとえば、1895年創業の水口酒造では、若き6代目が新たな醸造法や地元農家との連携に取り組みながら、「道後から世界へ」という挑戦を続けています。また、山田屋まんじゅうでは、東京でのキャリアを経て戻った後継者が、150年変わらぬ味を守りつつ、現代の感性で和菓子文化を再解釈しています。
一方で、今回のイベントの背景には、愛媛という地域そのものが持つ豊かな酒造文化の存在も忘れてはなりません。酒どころ=寒冷地という一般的なイメージに対し、愛媛は、実は全国でも有数の酒造技術を誇る地域です。
四国の中でも最多となる34の蔵元が存在し、かつての集約化の流れにも抗いながら、小規模ながら個性ある蔵が各地に点在しています。このように、「歴史ある文化資源を次世代へどう受け継いでいくのか。」その問いこそが、本イベントの大切なテーマのひとつです。
「DISCOVER EHIME」は、こうした背景のもとで生まれた、文化の継承と出会いの物語を『宿』という舞台で届ける取り組みです。
■ここでしか出会えない人と景色、技の共演
当日は、瀬戸内の穏やかな自然に包まれながら、地元文化を五感で堪能する特別な体験が用意されました。
<DAY 1:地酒とアートを愉しむ夜>
チェックイン後は、館内に点在する現代アートを巡るツアーを経て、山田屋まんじゅうが監修した和菓子&カクテルのペアリング体験へ。夕方は天候が変わり、会場を急遽「THE AONAGIスイート」へと変更。窓の外にはインフィニティプールが視界の下に広がり、落ち着いた雰囲気の中で特別な時間をお過ごしいただきました。 ディナーには、地元食材をふんだんに使用した懐石料理とともに、水口酒造がセレクトした希少な日本酒との特別ペアリングも提供。職人の手が生み出す美味の重なりに、参加者からは感嘆の声が相次ぎました。
ディナーには、地元食材をふんだんに使用した懐石料理とともに、水口酒造がセレクトした希少な日本酒との特別ペアリングも提供。職人の手が生み出す美味の重なりに、参加者からは感嘆の声が相次ぎました。 
<DAY 2:手しごとに出会う>
水口酒造を訪れ、醸造過程や酒米の選定へのこだわりを、蔵人たちの生の言葉で知るひとときに。1895年創業、道後で唯一の酒蔵を継ぐ6代目は、「道後から世界へ、世界から道後へ」を掲げ、地元農家との酒米づくりやクラフトビール、ラム酒など新たな挑戦にも挑み続けています。伝統の技を守りながら進化を重ねる蔵元が、酒造りにかける想いやこれまでの歩みを語りました。

続いて訪れた砥部町のヨシュア工房では、竹西辰人氏の案内で、藍の表現が美しい「ヨシュアブルー」の器の世界を体感しました。「ヨシュアブルー」は、10年の歳月をかけて生み出された独自の藍で、深海を思わせる吸い込まれるような青が特徴。伝統の技と現代の感性を融合させ、普段使いしやすい形やデザインを多数展開しています。 
■五感に触れる体験が、旅のあとも続いていく
今回のイベントでは、「地元の作り手と出会えたこと」や「食・器・空間に込められた背景に触れられたこと」が、滞在の記憶に深みを与えたという声が多数寄せられました。一部を抜粋してご紹介します。
- 通常の宿泊では出会えない、職人との交流や体験の流れ全てが新鮮だった
- 日本酒と料理のペアリングを楽しんだ翌日に、実際に作り手を訪れて話を聞けたのがよかった
- 美術館のような空間にアートが調和し、滞在全体が豊かに感じられた
- ブランドの世界観を五感で体験することができた
- アートギャラリー見学など、他のホテルでは味わえない体験ができた
- 食事は素材の良さだけではなく、それを引き立たせる手間を感じ、料理長のこだわりに感銘を受けた
■匠たちの言葉──出会いから生まれる未来
参加者が五感で受け取った感動の裏には、それを生み出す作り手たちの情熱と哲学があります。今回のイベントで出会った匠たちは、地域の文化を守るだけでなく、新しい挑戦を恐れずに続けています。それぞれがこの二日間を通して感じたこと、そしてこれから見据える未来を語ってくれました。
水口酒造
「青凪での開催は、県外のお客様に水口酒造を知っていただける良い機会でした。皆さん知的好奇心が高く、初めて味わうお酒を丁寧に楽しみながら、ご自身の好みを探している様子が印象的でした。中には普段日本酒をあまり飲まない方もいらっしゃいましたが、製造過程や背景のストーリーも含めて楽しんでいただけました。私たちの家訓は『暖簾を守るな、暖簾を破れ』。これからも愛媛の食と一緒に楽しめる新しいお酒づくりに挑戦していきます」
山田屋まんじゅう
「普段は宿泊施設への納品を通じた関わりが中心で、お客様と直接お話しする機会はほとんどありません。今回のような対話型イベントはとても貴重でした。中には、以前山田屋まんじゅうを召し上がったことのある方もいらして、とても驚きました。こうした偶然の出会いがあるのもイベントならではだと感じます。これをきっかけに県内外、そして海外にも認知を広げていきたいです」
ヨシュア工房
「砥部焼を引き継いで30年ほどになります。独自の藍『ヨシュアブルー』は、伝統の技法を尊重しつつ、吹き付けや色の調整で瀬戸内の海のグラデーションを表現した新しい色彩です。参加者が色や質感に感動してくれるのがとても印象的でした。250年の歴史ある砥部焼の中で、現代の感性を加え、日常でも楽しめる器を作り続けていきたいと考えています」
匠たちの言葉は、地域文化の奥行きと、その先に広がる可能性を感じさせてくれます。彼らの挑戦は、旅の一瞬を越えて、訪れる人の記憶と未来の風景をも変えていく——そんな余韻を残すものでした。
■「地域×宿泊」体験として、各地での展開を視野に
温故知新では、今後もその土地ならではの文化や営みを丁寧に掬い上げ、「ひとつの物語」として他の地域にも展開していくことを目指しています。
宿泊施設の開発にとどまらず、地域とともにつくる物語を軸に、旅の新しい価値を提案していく――。
私たちはこれからも、土地の声に耳を傾けながら、多様な地域と共創し、文化と風土を生かした唯一無二の旅の舞台を育てていきます。
瀬戸内リトリート青凪 by 温故知新について
-安藤建築の洗練された空間の中でアートを楽しむ-
一部美術館として公開されていた名建築を、2015年12月に設計者・安藤忠雄氏監修のもとリノベーションし誕生した、全7室オールスイートのスモールラグジュアリーホテル。ホテルのコンセプトは「Minimal Luxury」。安藤建築の洗練された空間の中、館内の随所にアート作品を展示。瀬戸内の旬の素材をふんだんに使用した懐石料理を提供するダイニングのほか、屋内外2つのプール、さらに四国初の本格ホテルスパも完備しています。
<施設概要>
施設名 :瀬戸内リトリート青凪 by 温故知新
所在地 :〒790-2641 愛媛県松山市柳谷794-1
電話番号 :089-977-9500(代表)
客室数 :全7室
アクセス :松山空港から車で約50分 / JR松山駅から車で約35分
松山ICより約40分 / しまなみ海道今治より北条R196経由約70分
羽田空港から松山空港経由で約3時間弱、空港送迎あり(有料)